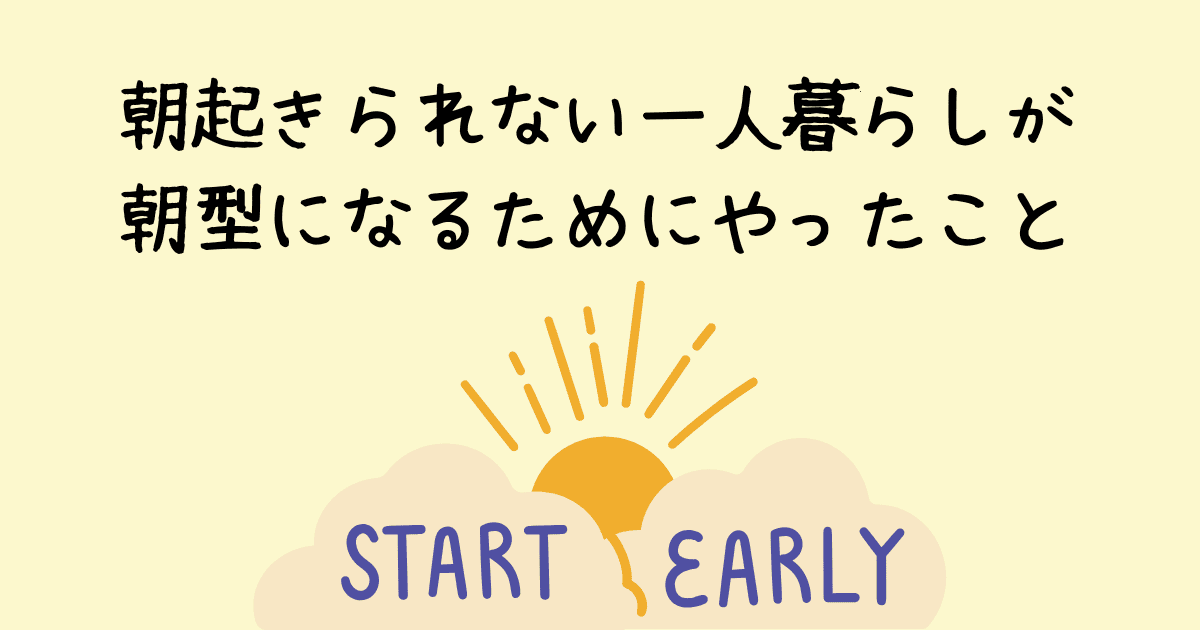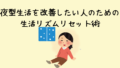朝起きなきゃいけないのに、気がつけば目覚ましを止めてまた寝てしまっている…。そんな日々に悩んでいませんか?
一人暮らしだと、誰にも起こされないし、遅刻しても怒られる相手もいない。だからこそ、自分で生活リズムを整えるのって本当に難しいんですよね。
私も以前は完全に夜型生活で、朝に起きることが苦痛で仕方ありませんでした。でも、ちょっとずつ朝型に近づく工夫をしたことで、今では朝時間を楽しめるようになりました。
この記事では、そんな私が実際に試して「効果があったこと」「合わなかったこと」を正直にまとめました。あなたの生活にも、無理なく取り入れられるヒントがあるかもしれません。
なぜ朝起きられない?一人暮らしで起こる原因
自由すぎる生活リズムが崩壊の元
一人暮らしだと、門限もなく、何時に寝ても誰にも文句を言われない自由があります。ですがその分、つい夜更かしを繰り返してしまい、体内時計が崩れてしまうのもよくある話。
「あともう少しだけ」とスマホをいじったり、動画を観ていたら深夜2時…なんて経験、あるあるですよね。この自由さが、朝起きるリズムを自ら壊してしまう原因になっていることも。
寝る前のスマホ習慣が睡眠の質を下げる
寝る直前までスマホを見ていると、脳が刺激を受け続けてしまい、リラックスできず眠りが浅くなります。結果として、朝起きても疲れが取れていない状態に。
私自身もベッドの中でSNSを見たり、動画を観るのが日課になっていましたが、これをやめたことで睡眠の質が変わりました。
緊張感がないと「起きる理由」が弱くなる
誰にも起こされない、家を出る時間も自分次第。そうなると、朝起きることへの必要性がどんどん薄れていきます。
私も「別に今すぐ起きなくてもいいや」と思って、2度寝・3度寝することが多々ありました。朝に起きる明確な“目的”や“理由”があるかどうかは、意外と大事なポイントかもしれません。
私が朝型に変わるためにやったこと

スマホは寝る1時間前に手放した
寝る前のスマホ習慣がどうしても抜けなかった私ですが、「画面を見ない時間を作ろう」と決めて、まずは寝る1時間前からスマホを別の部屋に置くようにしました。
最初は手持ち無沙汰で落ち着きませんでしたが、数日続けると気にならなくなり、その代わりに読書やストレッチの時間に変化。自然と眠気もやってきて、スムーズに入眠できるようになりました。
カーテンを少し開けて寝るようにした
遮光カーテンで朝の光を完全に遮断していたのをやめて、少しだけカーテンを開けて寝るようにしました。朝日が入ってくると、自然と体が目覚めやすくなります。
光目覚まし時計を導入するのも考えましたが、まずは簡単にできることから実践。これだけでも体内時計が整いやすくなった気がします。
モーニングルーティンを決めてみた
起きた後の流れを決めることで、行動がスムーズになりました。私の場合は「顔を洗う→白湯を飲む→音楽をかける→洗濯機を回す」という流れ。
毎日同じ行動をすることで、起きた直後でも“考えずに動ける”ようになります。最初はルーティンを紙に書いて、見える場所に貼っていました。
楽しみな予定を朝に入れてみた
朝に好きなことをする時間を作ることで、起きるのがちょっとだけ楽しみになりました。
私の場合は、「朝のカフェタイム」「アロマを焚く」「YouTubeでお気に入りのチャンネルを見る」など。小さなことでOKなので、“起きたくなる仕掛け”を作るのは意外と効果的でした。
睡眠ログアプリで記録してみた
起きた時間や寝た時間をアプリで記録して、睡眠リズムを見える化してみました。グラフで変化が見えるとモチベーションも上がります。
「今日は頑張って早く寝た!」という記録があるだけで、次の日も続けやすくなります。無料アプリでも十分なので、習慣化の第一歩としておすすめです。
やってみたけど合わなかった方法も正直に紹介
目覚まし時計を遠くに置く→無意識で止めてた
よくある「起きるための工夫」として、目覚ましをベッドから遠くに置いて、立ち上がって止めに行く作戦を試してみました。確かに一度は立ち上がるので効果があるように思えたのですが、実際には思った以上に自分が無意識で動いていたようで、気づいたら目覚ましを止めて布団に戻っていたんです…(笑)
目覚ましの音で目が覚めた記憶すらなく、「あれ、止まってる?」と気づいたときにはすでに寝坊していた、なんてことも。人によってはかなり効果がある方法かもしれませんが、私のように“寝起きの自分”の行動が読めないタイプにはあまり向いていなかったようです。
結局は、目覚ましの数を増やす、音の種類を変えるなど、別の工夫と組み合わせないと意味がないことがわかりました。試す価値はあるけれど、過信しすぎないことも大事です。
早く寝るだけでは効果がなかった理由
「早く寝れば朝起きられる」というのは理論上は正しいのですが、実際に早寝をしてみても、すぐに朝型になるとは限りませんでした。体がまだ夜型のリズムに慣れていると、布団に入ってもなかなか眠れなかったり、途中で目が覚めたりして、結局寝不足になってしまうことも。
私の場合は、ただ布団に入る時間を早めるだけではなく、“寝る前の行動”を丁寧に整えることがカギでした。具体的には、照明を落としたり、スマホを早めに手放したり、夜の過ごし方全体を見直すことで、スムーズに眠れるように変わっていきました。
つまり、「早く寝る=布団に入る」だけではなく、そこに至るまでの“準備”こそが重要だったんです。
サプリや寝具に頼りすぎない方がいいかも
一時期、どうしても寝つきが悪くて、快眠サプリや、ちょっと高めの枕やマットレスなどを試したことがありました。確かに、多少の心地よさは感じましたが、根本的な朝のつらさは変わらなかったんです。
その理由はシンプルで、生活リズム自体が乱れていたから。どんなに高性能な寝具やサプリを使っても、日々の習慣が整っていなければ効果は限定的。お金だけがかかって、思ったような成果は得られませんでした。
もちろん、自分に合う寝具を使うのは大切ですが、それ以前に“寝る時間や過ごし方を見直す”という基本を忘れないことが大切だと痛感しました。まずは習慣を変えてみて、それでも難しければ寝具を見直す、という順番がいいと思います。
朝型になって変わったこと・よかったこと
朝に余裕があるだけでストレス激減
朝起きてから出かけるまでの時間に余裕があると、それだけで心にも余裕が生まれます。以前の私は、起きてからバタバタと身支度をして、焦りながら家を飛び出す日々。そんな生活では、1日のスタートからすでに疲れてしまっていました。
でも、朝の時間を少しだけ早めに確保することで、コーヒーを飲んだり、音楽を聴いたり、気持ちにゆとりを持てるようになりました。そのおかげで、通勤中や午前中の仕事・予定も落ち着いて取り組めるようになり、結果的に1日全体がうまく回るように感じます。
ちょっとした時間の使い方ですが、この“朝のゆとり”が毎日のストレスをぐっと減らしてくれた気がしています。
朝ごはんを食べる習慣がついた
以前の私は、朝ごはんを食べる時間なんてないし、食欲もない…と毎日のように抜いていました。でも、朝時間に余裕ができたことで、まずは小さなパンやヨーグルト、バナナなどを食べるところからスタート。
すると体が目覚めやすくなり、午前中の集中力もアップしたのを実感。今では、朝ごはんの時間が“今日一日の準備”として欠かせないリズムになっています。
最近は、簡単なスープを作ったり、お気に入りのグラノーラを用意して「朝食を楽しむ」ことそのものが一つの癒しになっています。
1日が長く感じて充実度がUP
朝を有意義に過ごすと、その日1日がものすごく長く感じられます。これまでは「気づいたら夕方」という日も多かったのですが、朝から動くと午前中だけでもかなりのことができるんです。
洗濯や掃除を終わらせてから出かけたり、読書やブログを書く時間を作れたりと、自分のやりたいことにしっかり時間を使えるようになりました。その結果、「今日もちゃんと過ごせたな」と思える日が増え、自己肯定感や充実感にもつながりました。
朝型の生活に変えるのは簡単ではありませんでしたが、その分リターンも大きかったと感じています。
まとめ:少しずつ変えていけばOK
いきなり朝型になるのは難しいけれど、できることから少しずつ変えていけば必ず変化は出てきます。私自身も、数週間かけて徐々に変えていきました。
「無理しない」「完璧を求めない」「自分に合う方法を見つける」。これを意識するだけでも、朝がちょっとラクになります。
この記事の中で「これならできそう」と思うことがあれば、ぜひ今日から試してみてくださいね。